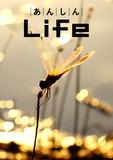農家出身の経営コンサルタント
二宮尊徳を訪ねて
小田原[ 神奈川県 ]
- 二宮尊徳
- 報徳二宮神社
- 小田原城
- 尊徳記念館
薪を背負った少年の銅像で知られる二宮金次郎。
のちに農民から武士となって、二宮尊徳と名乗り
各地の農村振興に尽力した。
多種多様かつ画期的なアイデアを実行した経世家であり
後世にも大きな影響を与える尊徳の足跡を追った。

向学心と地道な努力が
着実に実を結ぶ

報徳二宮神社の大鳥居は、創建120周年事業として、2017年に約3年かけて建立された。樹齢300年の小田原産の大スギを御用材とし、崇高な雰囲気が漂う。大鳥居をくぐって参道を歩くと、



左下/尊徳は56歳のとき、幕臣になった。
右下/二宮尊徳翁立像。大人になって現場を指導する姿を表現する
尊徳は、幼少の頃から勤勉で向学心旺盛だった。1787年に現在の小田原市
13歳のとき、父が亡くなった。尊徳は、母と弟2人の一家4人の生計を立てた。早朝に山で柴を刈り、昼は農作業、夜は縄や
18歳でわが家に戻ると少しずつ田畑を買い戻し、荒地を耕していった。23歳で購入した田畑は元の所有面積に達し、家の立て直しを事実上成し遂げた。
尊徳は、財政と農村再建の専門家としての道をまい進し始める。財政難にあえぐ小田原藩家老の
34歳のときには、小田原藩の命により
1837年、天保の大

小田原城は難攻不落の城として有名だ。戦国時代には、総延長9kmに及ぶ城と城下町一帯を、堀と土塁で囲む

左下/二の丸の表門に当たる銅門。大扉に飾られた銅を用いた金具に由来する
右下/敷地内で見事な枝を広げるイヌマキ。樹齢520年以上とされる

農業はもとより土木建築から金融、文学まで幅広い教養と優れた才能を持つ尊徳は、無私の精神で農民の安寧に尽力した。小田原市内には、尊徳にまつわる逸話が数多く残る。
酒匂川の堤防に植栽された約400本のクロマツ並木は、尊徳が植えたとの伝説がある。13歳の尊徳が、子守で得た駄賃で200本の苗を購入して植えたという。やがて並木となり、大きく根を張ったクロマツは治水に役立った。防風林としても田畑を守ってきたという。

栢山地区には
長期的な視点で自然環境の保全と街づくりに関わり、貧困や飢餓問題の解決にも取り組んだ尊徳の姿勢は、現代のSDGsに合致する。
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り1557文字 / 全文4186文字



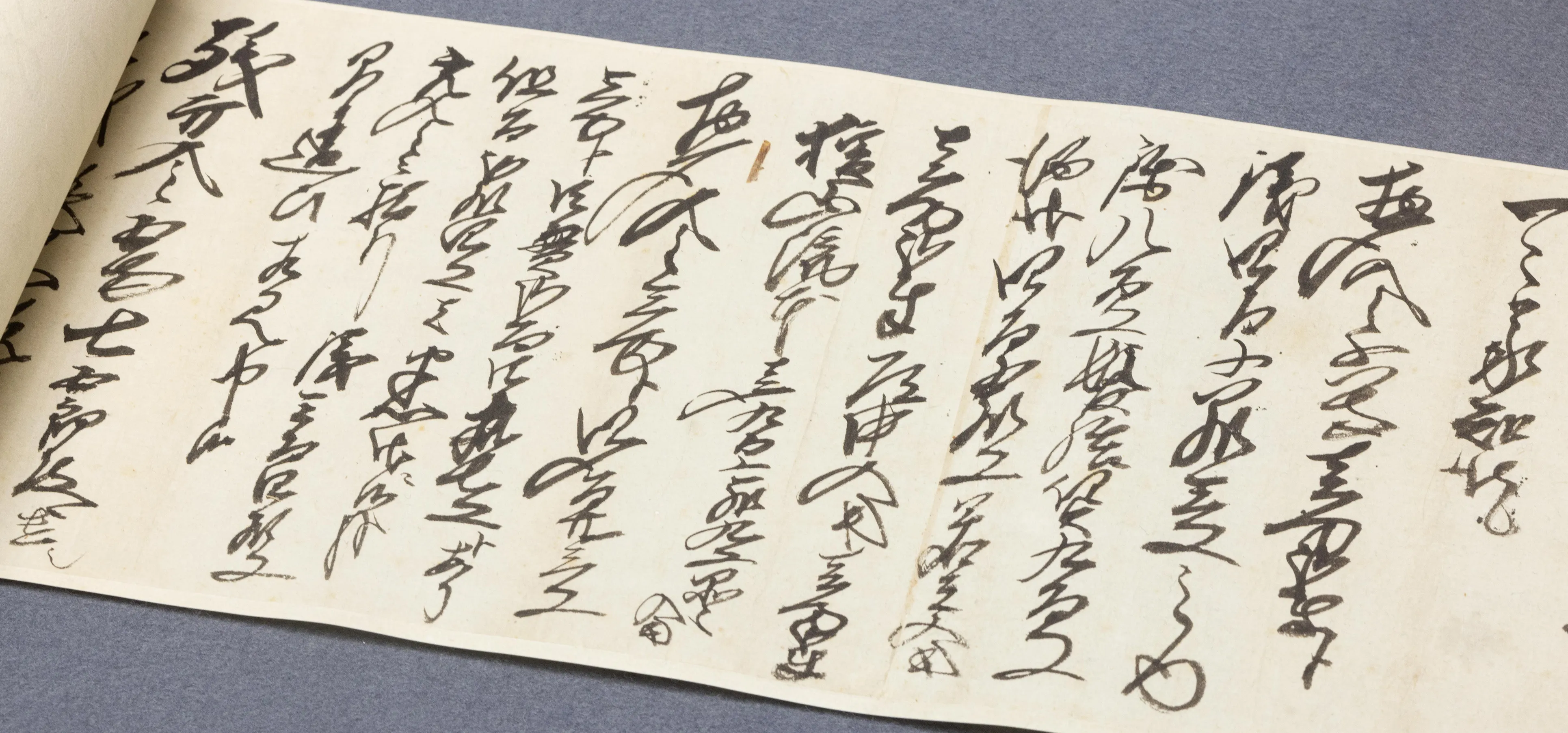
![金沢三文豪ゆかりの地を訪ねて 金沢 [石川県]](/assets_c/2025/12/thumb_202601-thumb-400xauto-803.jpg)
![改革の名君・上杉鷹山を訪ねて 米沢 [山形県]](/assets_c/2025/11/thumb_202512-thumb-400xauto-763.jpg)
![誇り高き幕末のリーダー・土方歳三を訪ねて 日野 [東京都]](/assets_c/2025/10/thumb_202511-thumb-400xauto-727.jpg)
![昭和の文豪・太宰治を訪ねて 津軽 [青森県]](/assets_c/2025/09/thumb_202510-thumb-400xauto-661.jpg)
![農家出身の経営コンサルタント 二宮尊徳を訪ねて 小田原 [神奈川県]](/assets_c/2025/08/thumb_202509-thumb-400xauto-608.jpg)
![藩の育成と繁栄を導いた伊達政宗を訪ねて 宮城 [宮城県]](/assets_c/2025/07/thumb_202508-thumb-400xauto-564.jpg)
![維新の立役者・坂本龍馬を訪ねて 高知 [高知県]](/assets_c/2025/06/thumb_202507-thumb-400xauto-542.jpg)
![人材教育を重んじた水戸藩を訪ねて 水戸 [茨城県]](/assets_c/2025/05/thumb_202506-thumb-400xauto-494.jpg)
![希代の名軍師・黒田官兵衛を訪ねて 姫路 [兵庫県]](/assets_c/2025/04/thumb_202505-thumb-400xauto-428.jpg)
![渋沢栄一の郷里を訪ねて 深谷 [埼玉県]](/assets_c/2025/03/thumb_202504-thumb-400xauto-397.jpg)
![横浜の発展に尽くした実業家を訪ねて 横浜 [神奈川県]](/assets_c/2025/02/thumb_202503-thumb-400xauto-340.jpg)
![織田信長の若き日の足跡をたどる 尾張 [愛知県]](/assets_c/2025/01/thumb_202502-thumb-400xauto-318.jpg)
![真田一族の本拠地を訪ねて 上田 [長野県]](/assets_c/2024/12/thumb_202501-thumb-400xauto-295.jpg)
![文豪たちが愛した街を歩く 文京区 [東京都]](/assets_c/2024/11/thumb_202412-thumb-400xauto-108.jpg)
![長州の維新志士を訪ねて 萩 [山口県]](/assets_c/2024/11/thumb_202411-thumb-400xauto-57.jpg)
![武田信玄が慈しんだ地 甲府 [山梨県]](/assets_c/2024/11/thumb_202410-thumb-400xauto-109.jpg)
![平城京の立役者を訪ねて 奈良 [奈良県]](/assets_c/2024/11/thumb_202409-thumb-400xauto-106.jpg)
![足利氏の源流を訪ねて 足利 [栃木県]](/assets_c/2024/11/thumb_20240708-thumb-400xauto-110.jpg)
![明治維新の偉人を訪ねて 鹿児島 [鹿児島県]](/assets_c/2024/11/thumb_202406-thumb-400xauto-107.jpg)
![近江商人を訪ねて 近江 [滋賀県]](/assets_c/2024/11/thumb_202405-thumb-400xauto-87.jpg)
![徳川家康ゆかりの地 浜松 [静岡県]](/assets_c/2024/11/thumb_202404-thumb-400xauto-56.jpg)