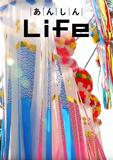日本の常識は世界の常識にあらず
意外と知らない世界の文化
タイの屋台文化に見る
自由で多様な食の楽しみ方

- 国名
- タイ王国
- 面積
- 約51万4000km2
- 人口
- 約6609万人(2022年 タイ内務省)
- 首都
- バンコク
- 言語
- タイ語
- タイ
- 屋台文化
- 中食が主流
- 年上を敬う
- ニックネームで呼び合う
この記事のポイント
- 中食文化が日常生活に定着していて、食を通じたコミュニケーションが活発
- 外国の文化を柔軟に受け入れ、独自にアレンジする国民性
- ビジネス上も「サバイ」(気楽にいこうよ)の精神。おおらかで寛容
東南アジアに位置する常夏の国・タイ王国は、東南アジアで唯一、植民地支配を免れた独立国だ。長い王朝の歴史を持ち、インドや中国といった近隣の国の影響を受けながら、独自の文化を築き上げてきた。歴史を象徴する多くの古代遺跡群を有し、世界遺産に登録されたアユタヤ遺跡、スコータイ遺跡は観光スポットとしても人気を集める。
タイの名物の一つが、タイで暮らす人々の胃袋を支える屋台文化だ。タイでは共働き家庭が多く、外食頻度が高いといわれる。特に都市部の家庭ではあまり自炊をしない。材料を買ってきて調理するより、外食で済ませる方がコスパが良いからだ。タイの屋台料理の値段は、バンコクなどの都市部で1品およそ130バーツ(570円前後)、郊外なら40バーツ(170円前後)ほどだ。家で食べる場合も、ごはんは炊くが、総菜やおかずは屋台や市場で購入するのが一般的だ。いわゆる中食スタイルである。

バンコクで人気のナイトマーケット。土産物の小物からファッション、フード、ドリンクなど多様な商品が並ぶ
1日の食事すべてを屋台で済ます人も決して珍しくない。朝食なら、おかゆとパートンコ(揚げパンに甘い豆乳を付けたもの)が定番だ。昼食や夕食には、パッタイ、クイッティアオといった麺料理や炒め物、カオパット(タイ風チャーハン)、ガパオなどが人気だ。
屋台では、味付けも自分好みに調整可能だ。料理の注文時に「○○を入れて」「○○は入れないで」とか、「辛くしないで」などと頼むことができる。
食事の量は少なく、回数は多く
屋台で売られる商品はバリエーション豊かだ。タイの定番料理の他、カットフルーツやイカの干物、揚げバナナなどタイのおやつ、オリジナルのシェーク、中には昆虫食を扱う店もある。屋台料理の多様さには、タイ国民の自由な発想力が表現されているといっても過言ではない。
2024年に屋台営業に関する規制が厳格化されたものの、もともと屋台は手軽に始められる商売の代表格だった。売りたい商品があれば誰でも開業できた上、テーブルや椅子を置く面積にも制限がなかった。そんなオープンな背景もあって、変わり種のお店も多く、その多様性が屋台文化をより魅力的なものにした。
もう一つ、食事1回当たりの量が少ないのもタイ人の特徴だ。例えば、タイのインスタントラーメンを見ると、日本のものと比べて3分の2程度と小さい。その代わり間食の回数が多く、軽食を含めると1日4-5回、食事をするケースも珍しくない。
実は、1回の食事量が少ない理由は味の濃さ、辛さにも関係していると考えられている。ソムタム(青パパイヤサラダ)や麺類など、多くの料理にはしっかりとした味付けと辛味があることで、胃袋に物理刺激を与え、少量でも満足感を得られるからだ。ただし腹持ちが悪いのは否めず、少量の食事をちょこちょこ食べる習慣が根付いたとされる。これがまた、多様な屋台文化が発展した理由の一つかもしれない。
新しいものを取り入れ融合させる国民性
タイの人々にとって外食は、コミュニケーションの場としての役割も大きい。「お祝いだから」「仏教の日だから」「日曜だから」と理由をつけて「外食しよう」という流れになる。食事は、お互いの仲を深める大切な手段なのだ。
料理もおいしさだけではなく、エンターテインメント性のあるものが好まれる。最近は日本のしゃぶしゃぶとすしがセットになった「SHABUSHI(しゃぶし)」が人気だ。SHABUSHIは1人ずつ用意されたしゃぶしゃぶ鍋に好みの味のスープを入れ、回転ずしのように流れてくる肉や野菜を入れて食べる料理だ。以前は、すしもレーンに流れていたが、今は自分で取りに行くビュッフェ方式が主流だ。

カラフルでかわいい「ルークチュップ」。緑豆やココナッツミルクを使ったタイの伝統菓子だ。
SHABUSHIに限らず、タイの日本食にはタイ文化を感じさせるアレンジが加えられたものが多い。すしは、タイ人の苦手な生魚ではなく、加熱した食材を多くネタに使う。握りずしのサイズは、日本のものより小さい。カラフルなすしが並ぶ様子は、タイの伝統菓子「ルークチュップ」を思わせる。タイならではの光景だ。
タイで日本風の定食を頼むと、キムチが付いてくることが多い。辛い物好きな人が多い、タイならではの配慮だ。
このようにタイの人々は、新しい文化を積極的に取り入れ、既存の文化と融合させるのがうまい。"タイ流の日本食"を見るだけでも、彼らの柔軟性や楽しさを追求するポジティブな国民性がうかがえる。
タイの食事方法にも触れておこう。タイでは基本的にスプーンとフォークを使用する。箸は麺類(主に汁麺)を食べるときに用いる。カオニャオ(モチ米)を食べる際には手で食べるのも日常的だ。一方、日本と違い、器に口を付けるのはマナー違反だ。汁物を飲むときは必ずレンゲ、またはスプーンを使うようにしよう。
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り1761文字 / 全文4025文字
宇都宮 由佳
学習院女子大学国際文化交流学部 教授