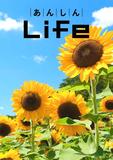日本の常識は世界の常識にあらず
意外と知らない世界の文化
入浴はシャワーのみで湯船につかる文化はない!?
オーストラリア人の
節水ルール、ウソ・ホント
- 国名
- オーストラリア連邦
- 面積
- 768万8287km2
- 人口
- 約2720万人(2024年 豪州統計局)
- 首都
- キャンベラ
- 言語
- 英語
- オーストラリア
- 節水文化
- バーベキュー好き
- 多文化主義
この記事のポイント
- 節水意識は高いが、ネットの極端なルールは誇張も多い。実態はより現実的
- 多文化主義を打ち出したことで先住民を尊重し、多様な文化背景を持つ人々の共存を目指す
- 家族ぐるみでバーベキューなどに招待するのがオーストラリア流コミュニケーション
オーストラリア連邦は、オーストラリア大陸本土と多数の周辺諸島から成る連邦立憲君主制国家だ。自然豊かな国土には「グレート・バリア・リーフ」やウルル(エアーズ・ロック)を有する「ウルル=カタ・ジュタ国立公園」をはじめ20の世界遺産がある。
国土の大半が乾燥地帯または半乾燥地帯で、特に降水量が少ない内陸部には砂漠も多い。汚水の処理に手間がかかるうえ、10年に一度は大規模な干ばつが起こる。日ごろから水を大事にする習慣が根付く。
子どもの頃から水の使い方に注意を払う教育がなされるほど、オーストラリア人の節水意識は高い。その半面、留学生や移住者向けのサイトには「誇張された節水ルール」の情報が多く掲載されている。キャンベラ、シドニー在住のオーストラリア人の意見を参考に、ネット情報の真偽を検証していこう。
まず「入浴はシャワーのみ。湯船につかる習慣はない」だ。確かにシャワーで済ませる人も結構いそうだが、湯船につかるのを好む人も多い。お風呂グッズもよく売られている。もっとも、スペースの関係で、都市部ではバスタブのないアパートメントが多い。
「シャワーを使う時間が短く、4~5分以内が目安」という説も怪しい。適宜、水を止めながら使ったとしても、十分な時間ではないだろうか。
「毎日髪を洗う習慣がない」も正確には人それぞれだ。オーストラリアにも毎日洗う人は普通にいる。「洗濯はまとめて行う」「洗顔時や手洗い、歯を磨くときは適宜水を止める」もごく普通のことなので、わざわざ取り上げて言うほどではない。「節水の意識を持とう」という印象だ。
「食器洗いはチョロチョロの水量でさっと流す、もしくはペーパーで拭き取る」も一般的とはいえない。今ではオーストラリアの家庭の多くが食器洗浄機を使用し、手洗いよりも使用水量が少ない。汚れをペーパーで拭き取る人は存在するが、これも個人の価値観によるだろう。
「政府が推奨する節水法には『トイレの小は流さない。流すときは大とまとめる』ルールがある」という極端な説もあった。もちろんそんな話は一般的ではない。これは深刻な干ばつのとき、もしくはある砂漠の街で誰かが体験した特殊な事例に尾ひれがついた可能性が高い。
「洗車時はホースの使用禁止」については、深刻な干ばつ時でも、流しっぱなしでなく、ホースの手元にある水を止めるボタンで調整すれば問題ないとされていたようだ。
水に対する規制はオーストラリア全土の共通ルールではなく、州や自治体によって異なることも覚えておこう。オーストラリアでは州の権限が強く、州ベースで独自のルールを定めている。極端なルールを実践すると、逆に現地の人にギョッとされることもあるので、ネットの情報をうのみにしないよう十分に注意しよう。
日本人が知らないオーストラリアの歴史

オーストラリア人と仲良くなるうえで知っておきたいのが、彼らの歩んできた歴史と現在の文化に至るまでの背景だ。
オーストラリアは先住民をはじめ、英国を中心に世界各地からの移民が共生する多民族国家である。国全体の人口比も海外生まれが全人口の3割近くを占め、両親のどちらかが海外で生まれた移民2世も含めると、その割合は5割を超える。
今でこそ誰もが法の下で公平に扱われる「平等主義」(Fair Go)が基本理念とされているが、過去には英国人による先住民への迫害や、非白人の入国制限、在住アジア系住民の国籍取得を困難にする排他的な政策が取られた時代もあった。だが、1970年代に多様な文化を尊重しながら平等な社会を目指す「多文化主義」政策が打ち出されたのを機に、多様な文化や価値観を受け入れ合う意識が醸成されていった。
先住民の土地の所有権をめぐって、92年にオーストラリアの連邦最高裁判所が示した「マボ判決」で、18世紀に植民者の英国がオーストラリアを「無主の地」(所有者のいない土地)として領有したことの正当性を問い、「オーストラリアは先住民の所有する土地だった」と先住権を認めたことも大きな転機だ。これにより、オーストラリアの住民たちは「何万年もこの土地に住み続けた先住民を敬わなければいけない」という考えを共有するようになった。
その一環として行われているのが「アクノレジメント・オブ・カントリー(Acknowledgement of Country)」という、その土地の伝統的な所有者に敬意を表す儀式だ。セレモニーやイベントの開始時に、そこの土地を管理してきた先住民に対する感謝と尊重の言葉を宣言したり、建物の看板およびWebサイトのトップページにメッセージを表示したりして「この土地は先住民のものである」と思い出させる目的がある。
これらに加え、日本人は学校教育で教えられなかったオーストラリアとの戦争の歴史も知っておく必要があるだろう。なぜならオーストラリア人にとって、第2次世界大戦(特に太平洋戦争)は対日戦争として認識されているからだ。オーストラリア本土に爆弾を投下した唯一の国は日本であり、北部の都市ダーウィンには碑が建てられ、日本軍による爆撃の記録が刻まれている。東南アジアにおける、日本軍のオーストラリア人捕虜に対する扱いも非常に過酷だった。これらの歴史は学校でも教えられ、小説や映画などの題材にもなっている。
現在のオーストラリアは親日国だが、一部には反日感情を持つ人もいる。歴史を知らないと相手に失礼に当たる場合もある。自ら話題に出す必要はないが、相手を敬う礼儀として把握しておくことをおすすめしたい。
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り1960文字 / 全文4527文字
飯笹 佐代子
青山学院大学総合文化政策学部 総合文化政策学科 教授