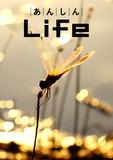日本の常識は世界の常識にあらず
意外と知らない世界の文化
枠にはまらないのが"らしさ"
マレーシアの付き合いに見る
多様な価値観の受け入れ方
- 国名
- マレーシア
- 面積
- 約33万km2
- 人口
- 約3350万人(2023年 マレーシア統計局)
- 首都
- クアラルンプール
- 言語
- マレー語(国語)、中国語、タミール語、英語
- マレーシア
- 暮らしやすい
- 多様性国家
- 失敗に寛容
この記事のポイント
- 他民族、他宗教の人ともお祭りを祝う「オープンハウス」が多様性を育む
- ワークライフバランス重視でも、日本より高い経済成長率を維持
- 食事に誘うときは、事前に相手の希望を聞くことが大切
東南アジアの中心部に位置するマレーシアは、マレー半島南部とボルネオ島北部の一部から成り立つ連邦立憲君主制国家だ。国土の約6割が熱帯雨林に覆われた自然豊かな国で、世界自然遺産に登録されたキナバル自然公園やグヌン・ムル国立公園を有する。ヨーロッパ植民地時代の建築物や文化が残るマラッカとジョージタウンは、世界文化遺産に登録されている。
比較的治安が良く、物価の安さや生活水準の高さから、自国民はもちろん外国人からも暮らしやすく居心地の良い国として評される。その根底にあるのは、マレーシアならではの多様性に対する「寛容さ」だ。
マレーシアは、国民の約7割を占めるブミプトラ(マレー系とその他の先住諸民族)を中心に、中華系、インド系が共生する多民族・多宗教国家である。異なる文化や価値観を持つ人々が平和に共存するのは、お互いの違いを寛容に受け入れる意識が社会に根付いているからだ。
マレーシア国民には、「自分たちの価値観だけを100%実現するのは難しい」という共通認識がある。加えて、互いの価値観を尊重し合ったり、自身と異なる意見ともうまく折り合いを付けたりする柔軟性も併せ持つ。そのため、外国人に対しても比較的オープンな人が多い。これもマレーシアが暮らしやすく居心地が良いと感じさせる一因だろう。
ただフレンドリーなだけでなく、必要に応じて適切な距離感を保ちながら付き合うすべにたけているのもマレーシア人の特徴だ。「信仰や文化が違うと、踏み込んではいけない部分もある」という配慮から、自然に身に付いたものといっても過言ではない。
人付き合いではその都度、相手と向き合う姿勢が大切

一緒に食事するのは、仲良くなる近道。相手の宗教や主義で食べられないものは事前に確認しておこう
多様な価値観を持つ人々が共生するマレーシアでは、その場ごとに相手のマイルールを理解し合う姿勢を持つのがコミュニケーションの重要なカギとなる。
特に重要なのが、宗教や食事にまつわる個人的なルールを聞くことだ。マレーシア人の約60%はムスリム(イスラム教徒)だが、教義に対する解釈や許容度は人によって大きく幅がある。ムスリムに限らず、仏教徒、ヒンドゥー教徒、ベジタリアンも、何をどこまで許容するか、NGとするかもその人ごとに異なる。相手を困らせたり、不快な思いをさせたりしないよう、「●●の人はこれが当たり前」という思い込みは捨てて、相手に希望を聞いてみよう。
マレーシアの人々と仲良くなるには相手の好みやルールを聞いた上で、お茶や食事に誘うと距離を縮めやすい。もし、ムスリムやベジタリアンなど、異なるルールを持つ人同士で集う場合は全員で話し合い、最大公約数的な場を探すと良いだろう。
ただし、異性間ではある程度の距離感が必要な人もいる。一方的な押し付けにならないように注意しよう。同性であれば気軽に声をかけても良いだろう。
マレーシアの人々は家族の結び付きを大切にする。世間話で家族の話をするのもおすすめだ。相手の話を聞くだけでなく自分の家族の話も伝えると、より親近感を抱かれやすくなるはずだ。もし、ニックネームで呼ばれるようになったり、家に招いたりしてくれるようになったりしたら、親しみを感じてもらえた可能性が高いと捉えて良いだろう。
日本の常識に固執せず、個々のルールを尊重する
コミュニケーションを取る際に注意したいのが、握手を強要しないことだ。個人差はあるものの、ムスリムは男女間で握手をしない人が多い。ムスリム以外の信仰を持つ人が相手でも、男女間の適切な距離はそれぞれ異なる。相手が手を出さない場合は、自分から握手を求めないほうが無難だ。
ムスリムが相手の場合は、左手で握手や物の受け渡しをしないのも大切なマナーだ。イスラム教では左手が不浄とされ、必ず右手を使うようにしたい。加えて男女問わず、初対面のムスリムと接するときは肌の露出を控えよう。特にややフォーマルな場では肌の露出を控えた長袖の服を着るのが礼儀であり、相手へのリスペクトを示すことにもつながる。
飲酒も気を付けるべきポイントの一つだ。マレーシアでは人前で酔っ払うと、自己コントロールができない人と見なされる。節度ある飲酒を心がけるのはもちろん、飲まない人に無理に飲酒を勧めるのも避けよう。
何より大切なのは、日本人が考える「日本社会の常識」をマレーシアに当てはめない点だ。常識の違いや、一人ひとりの価値観を受け入れる感受性を高める試みは、多様性を理解する一歩につながるはずだ。
多様な人たちが交流を深め合う「オープンハウス」
マレーシアの平和共存を象徴する行事のひとつが、祝日に自宅を一般公開し、宗教・民族を問わず人を招いて飲食を共にする「オープンハウス」だ。一番典型的なのは、イスラム教のラマダン(断食)明けの祝日に行われる「ハリラヤ・プアサ」だ。中華系の中にも、春節の際に自宅を開放して多様な人たちとの交流を深める人がいる。

家でハリラヤ・プアサを祝うムスリムの家族。異なる宗教、民族の人が招かれるのも珍しくない
違う信仰の祭りを祝うか否かは、個々の判断にゆだねられる部分が大きい。本人がOKという考え方なら、キリスト教徒以外でもクリスマスを祝う人もいる。こちらから企画を立てる場合は、人それぞれの宗教観を尊重しながら話を進めるようにしよう。
多くの宗教が共生する分、お祭りの種類も多様だ。代表的なものは連邦全体の公休日や祝日に定められている他、州ごとの祝日も多い。祭りに参加しなくても、祝日そのものを休日として楽しむのが一般的である。
信仰ごとに有給休暇を取るタイミングも異なる。ムスリムならラマダン(断食)明けに帰省したり、中華系の人なら春節にまとめて休みを取ったりする。職場で人員が手薄になっても、"お互いさまの精神"で仕事を回し合うのは、マレーシアでは当たり前の光景だ。この柔軟に支え合う関係性のあり方は、育休や介護休業の取得が増えつつある日本社会でも、大いに見習いたい部分だ。
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り1974文字 / 全文4715文字
左右田 直規
東京外国語大学大学院総合国際学研究院 教授