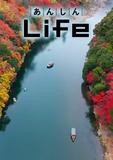日本の常識は世界の常識にあらず
意外と知らない世界の文化
オクトーバーフェストで盛り上がろう!
歴史も味わいも深い
ドイツのビール文化

- 国名
- ドイツ連邦共和国
- 面積
- 約36万km2
- 人口
- 約8360万人(2024年 ドイツ連邦統計庁)
- 首都
- ベルリン
- 言語
- ドイツ語
- ドイツ
- ビール祭り
- 農業大国
- 温かい料理は昼食だけ
この記事のポイント
- 収穫の秋に古いビールを飲み干すのがオクトーバーフェストの起源
- ハム、ソーセージ、ビールは長い冬を乗り切る保存食として発達
- ドイツ人に自宅でのランチに誘われたら距離が近づいた証拠
西ヨーロッパに位置するドイツ連邦共和国は、国土の3分の1が森で覆われた自然豊かな国だ。ユネスコの生物圏保存地域に登録されたシュヴァルツヴァルト(黒い森)や、奇岩が連なるザクセン・スイス国立公園をはじめ、自然を満喫できるスポットが点在する。
EU屈指の農業大国でもある。冬の寒さが厳しい北部では、麦類やジャガイモといった耐寒性のある農作物が栽培される。酪農が盛んな中南部は、ハムやソーセージのような保存食やチーズの産地としても名高い。
ドイツを語る上で外せないのが、ビール文化だ。ドイツは世界有数のビール大国で、生産量、消費量共に世界シェアの上位に数えられる。国内には約1500の醸造所があり、5000種類以上の銘柄が存在する。
ビール醸造の起源はメソポタミア文明までさかのぼる。ドイツでは8世紀ごろから修道院で造られるようになったと伝えられる。当時の修道院はコミュニティーとしての機能を持ち、パンや薬といった暮らしに必要なものを自給自足で賄っていた。ビールの醸造もその一環で、修道院ごとに様々な種類のビールが造られた。ただ、使用する原料の違いにより、味や品質にはばらつきがあった。
1516年にビールの原料は大麦・ホップ・水・酵母のみと定めた「ビール純粋令」が制定されて以降は、ドイツビールの品質は大幅に向上し、国際的にも高く評価されるようになった。
世界最大規模のビールの祭典「オクトーバーフェスト」

ミュンヘンの名物オクトーバーフェストには、毎年600万人以上が訪れるという
1810年にミュンヘンで行われたバイエルン皇太子の結婚式を機に、「オクトーバーフェスト」は国民的行事として定着した。今でこそ、世界最大規模のビールの祭典として広く知られるものの、元々はビールの醸造シーズン幕開けを祝う地域の祭りだった。冷蔵技術がない当時、ビールの保存は難しかった。新しいビールを造る前に、古いビールを飲み尽くす目的があった。
近年は日本でもオクトーバーフェストを模したイベントが開催されるようになったが、本場ドイツの催しと異なる点は多い。日本では春先や夏場にも開催されるが、ドイツでは必ず9~10月に行う。日本は350ml、500mlのグラスをよく使うのに対し、ドイツ南部では1Lのジョッキがスタンダードである。
もし日本で本格的なドイツビールを味わうなら、専門店で品質の良い銘柄をおすすめしたい。
ワインや食料品にも共通するように、ドイツには「安かろう、悪かろう」な商品が多いからだ。ケルン独自のビール「ケルシュ」も30種類以上の銘柄があり、高いものほど味が良い傾向がある。ドイツで食材を買う際は、安さで選ばないよう心得ておこう。
ちなみに、変わり種のドイツビールとしておすすめしたいのが、バンベルクの「ラオホビア(燻製ビール)」だ。ビール醸造所が火事になって、偶然いぶされたビールがおいしかったのが由来とされ、独特の焦げた風味が味わい深い。日本国内で取り扱う店もあるので、ぜひ味わってみてほしい。
缶か瓶か。飲む温度は? ドイツ人のビールへのこだわり
ドイツ人は缶より瓶のビールを好む。瓶は鮮度が高くておいしい上、再利用しやすく手軽だからだ。基本的にはグラスに注いで飲むが、カジュアルな場では瓶のまま直接飲む人が多い。学生同士のパーティーでは未開栓のビールを手渡される。栓抜きを持ち歩く人も珍しくない。たとえ栓抜きがなくても、たいていの人は机の端やライター、スプーンを使って栓を開けるテクニックを持っている。
ビールの鮮度にこだわるドイツ人は、意外にも温度にはさほどこだわらない。飲み会では、野外でぬるくなったビールを飲むことも多い。例えば日本人留学生にとっては、「学生同士で冷えていないビールを飲んだ回数」は、ドイツ人学生との親交の深さを示すバロメーターにもなっている。
調理法より鮮度を重視する
醸造されるビールと同様、食事に関しても地域での違いが大きい。日本人にとっては、ラインラント、ベルリンなどの北ドイツよりも、ミュンヘンなどの南ドイツのほうが味覚が合い、おいしいと感じる料理が多いといわれる。
寒冷地であるドイツの食生活は昔から質素だ。内陸の都市では魚を食べる習慣があまりない。特に冬場は、ハムやソーセージ、ザワークラウト(酢漬けキャベツ)といった保存食が中心となる。ハムやソーセージ、パンの種類が豊富とはいえ、調理のバリエーションが少なく飽きやすい一面もある。IHや電気コンロを使った調理が主流のためか、火加減を重視する凝った料理も少ない。野菜は生で食べるのが一般的である。

ザワークラウトや加工肉などは、長い冬を乗り切る保存食として定着した
1日の食事で最も大切なのが昼食だ。地域や家庭によって様々で、現在はずいぶん変わりつつあるようだが、ドイツでは昼にソーセージやシュニッツェル、煮込みといった温かい料理をしっかり食べる伝統がある。朝食と夕食は、火を使わない「カルテス・エッセン(冷たい料理)」としてパン、ハム、チーズ、野菜を軽めに食べる人が多い。
レストランでも店によっては、夜だと注文を断られる料理がある。そのひとつが、ゆでて皮を剥いて食べる白ソーセージ「ヴァイスヴルスト」だ。朝作って昼に食べる考えの背景には、新鮮なものを新鮮なうちに食べるのがぜいたくという価値観の影響もあると思われる。
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り1650文字 / 全文4113文字
森 貴史
関西大学文学部総合人文学科文化共生学専修 教授